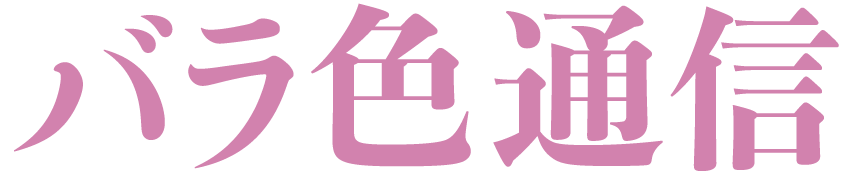第14回 イタリアが僕にくれたもの⑤

鎌倉暮らしやイタリア生活で出会ったあれこれをお届けしているこのコラムですが、昔を振り返って、僕がアパレル業界に足を踏み入れてからイタリアに渡り、帰国して今に至る経緯についても少しずつお話ししていきたいと思います。
題して、「イタリアが僕にくれたもの」。
コラム内シリーズとして不定期にお届けしますので、時代の空気を感じ取っていただけたらうれしいです。
今回はその第5回です。
デザイナーがイタリア駐在員に転身したその訳は? その2
人生初めてのコニャックを恐る恐る舐めていると、横にいる社長が本題を語りはじめた。
なんでもイタリアで新進気鋭のデザイナーと知り合い、彼のお膝元フィレンツェに彼の店を出してあげることにしたらしい。
他にも工場のジョイントベンチャーやら、バイイングオフィス創設やら諸々あったが、要はそれらの管理をするために誰か会社から常駐を置きたいという話だった。
時は1990年9月、バブル期の頂点。
一つのマンションブランドだった会社が飛ぶ鳥を落とす勢いで、倍々成長し、自由が丘に出した直営店はあの田中康夫著『なんとなくクリスタル』にも実名で取り上げられるほどの時代の寵児となっていた。
勢いに乗っていた社長の興味はアパレルに飽き足らず、ライフスタイルブランドの設立、ヨーロッパ生産開始、そして海外デザイナーの発掘へと急速に進化していた。
社長「で、今朝の会議で幹部全員が君が適任だということなんだけど、どう?」
蜂谷「へ」
寝耳に水とはまさにこの事だ。何かで叱られるもんだと思って臨んだ会食だったので、拍子抜けどころか、想像を越えた話で二の句が継げなかった。
たまたま転がってきたデザイナー職、諸先輩に縋りながら続けて3年半になろうとしていた。
自分は飽き性なのか、新しいことに目移りし易い。すでに形をデザインする事はアシスタントに任せて、生地デザインやディスプレイ(その当時ビジュアルマーチャンダイジングという言葉はなかった)に執心していた。
どうも50歳になった時の自分が、婦人服のデザイナーを続けているイメージがうまくできなかった。
そもそも自分が着ない服をデザインするというのは、あくまでも流行を察知し、そのブランドの顧客が好みそうなものを製品化する作業を続けることであって、その連続が果たして自分がやりたいと感じていることなのか、よくわからなかった。
もちろん、飛び級で営業職からデザイナー職へ道をつけていただいた社長本人には、そんなことおくびにも出せるわけがない。
蜂谷「急なお話なので、返事は少しお時間いただきたいのですが、今考えていることを話させていただいてもいいですか…?」
社長「おぉ、もちろん」
自分の性格だと思うが、見境無くその時思っていることを口に出してしまう癖がある。
その頃はぼんやりと海外を駆け巡る仕事に憧れていた。その時にやっていた仕事を考えるとまあ叶わぬ夢だ。
「働く」は 「学ぶ」でも良かったが、28歳にもなって学生で海外なんて有り得ないから、仕事でーーその程度の発想だった。
見栄っ張りな性格なので、英語を使って飛行機で移動を繰り返すことだけへの憧れ。
ゼロハリバートンのスーツケースにステッカー貼りまくって…。まあ、ミーハーで幼稚な考えだ。
そんなことや頭にあった仕事観をつらつらと話していた。なぜその話をしたのかはわからなかったが。
社長「じゃあ、もうバッチリじゃないか!」
社長「もう一軒行こう!」
促されるままに外に出て、止まったタクシーに乗り込んだ。
社長「銀座8丁目のポルシェビル行って」
蜂谷「(今度は銀座か…。家から遠くなるな)」
しかし社長命令は絶対だ。
車を降りると平日にも関わらず、歓楽街は人でごった返していた。
ビルの中から人ごみをかき分けてどこか旅館の番頭さんのような方が、社長に声をかけてきた。
こんなところでも知り合いに会うのかと思ってみていると、その方と一緒にビルのエレベーターに乗り込むことになった。
その方は僕のような青二才にまで丁寧に挨拶をしてくれた。
扉が開くと目の前に和装もしくはドレスで着飾った綺麗な女性が何人も見えた。
辿り着いたのは銀座では屈指の有名店『グレ』で、先ほどの方は本当の番頭さんだった。
人生初の銀座のクラブ突入!
社長と僕はホステスのおふたりと案内されたボックス席についた。ボーイさんが素早くおしぼりやら灰皿を彼女たちに渡す。
社長が彼女たちと盛り上がっている間に、熱いおしぼりで蒸気した顔を拭きながら、暗めの照明にも慣れたので、周りの様子を伺った。
大きな花生けがあちこちに飾られている。客はほぼスーツ姿のおじさん達だ。テレビドラマでしかみたことのない風景がそこにあった。
ホステスさんのどなたかが誕生日らしい。社長は「じゃあ、入れてあげよう。」と上機嫌だ。
瞬く間にシャンパンが登場し、僕らはいつの間にか、5、6人のホステスさん達に囲まれていた。
社長「こいつうちの社員なんだけど、イタリア駐在が決まったんだよね。」
ホステスA「それではお祝いですね、ぜひ乾杯しましょう!」
蜂谷「いえ、いや、それはまだ決めったわけではなくて…」
全員「カンパーイ!」
自分のモゴついた声なぞ、あっという間に掻き消された。
「返事は少し待って…」が六本木から銀座に移った間に決定事項となっていた。
クラブが女の人に触れる場所じゃないことを確認したところで、12時の閉店で店を出された。
バブル絶頂期にタクシーの空車なぞ平日だろうがそんなゴールデンタイムに存在しないのだった。
社長曰くハイヤーの予約が1時間後に取れたらしい。送っていただけるとのことで、高級そうなおでん屋でそれを待つこととなった。
最後はおでんを肴に日本酒だ。
もう既に何を話したのか、何を食べて飲んだのか記憶はほぼ無かった。
上司を前に飲まないなど有り得ない時代だった。
社長は横浜に住んでいたので、私を瀬田で降ろして第三京浜で帰ってくれるらしい。
銀座から夜の首都高に乗った。
クラッシュ寸前の自分を見かねて、社長が優しく窓を開けてくれた。
まだ煌々と明かりの点くビル群が続いていたことだけは鮮明に憶えている。
用賀を降りて瀬田の交差点に着いた。社長に家の前まで送るよと言っていただいたが丁重に断って、そこで降りた。
首(こうべ)を垂れて今日の礼を言い、車を見送った。
深夜1時半、垂らした首をあげる前にその日収めたホッピー、コニャック、シャンパン、日本酒ともお別れし、信号が変わるのを待ちながら、「またゼロからか…」と空を仰いだ。

運命が変わった銀座にて。
Author 蜂谷 雅彦(Masahiko Hachiya)
大人のためのコンフォート、ジェンダレス、エイジレスな服を提案する「HACHIYA」デザイナー。
アパレル駐在員として長くイタリアに在住し、帰国後はグッチをはじめとするハイブランドのマーチャンダイジングを手がける。
現在は、デザイナー、ライフスタイルコンサルタントとして活躍しつつ、海を望む鎌倉の家から、サバーバンライフを発信中。
HACHIYA online
https://hachiyaonline.com/
Instagram
https://www.instagram.com/ipermasa/
https://www.instagram.com/hachiya_online/
HACHIYA CHANNEL
https://www.youtube.com/channel/UCrWxUwF5bVGyds2a2BH9Z5A